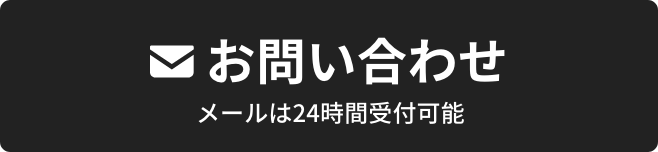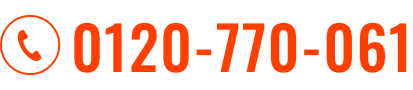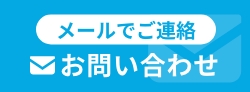大規模修繕
大規模修繕工事とは何か?建物価値を守るための基礎知識と埼玉県坂戸市の丸投げアパマンの安心サポート

マンションやアパートなどの集合住宅では、時間の経過とともに建物の外観や設備の劣化が避けられません。日常的な清掃や小規模な修繕だけでは維持できない部分も増え、やがて「大規模修繕工事」という形で建物全体のメンテナンスを行う必要が出てきます。
大規模修繕工事とは、建物の機能や美観を維持・回復するために、共用部を中心に計画的・総合的に実施される工事です。たとえば外壁の塗装、防水工事、給排水管の取り替え、エレベーターやインターホン設備の更新などが含まれます。
こうした工事は、一戸建てのように「壊れたら直す」という単発的な修繕とは異なり、中長期的な視点での計画と資金の確保、さらに住民全体の合意形成が必要となるため、非常に重要でかつ繊細なプロセスになります。
本記事では、
– 「大規模修繕工事とは何か」
– 「どのくらいの周期で必要になるのか」
– 「修繕費の相場や費用の内訳」
– 「失敗しない業者選び」
– 「地域密着の『丸投げアパマン』のサポート」
といったテーマを中心に、これから修繕計画を立てようとしているオーナー様や管理組合の方々にとって役立つ情報を、わかりやすく丁寧に解説していきます。
修繕のタイミングを見極め、適切な予算と業者で計画的に進めることは、資産価値を守り、入居者の満足度を維持する上でも非常に重要です。ぜひ最後までご覧いただき、「じゃあ、うちはどうすべきか?」を一緒に考えてみましょう。
Table of Contents
大規模修繕工事の基礎知識

大規模修繕工事とは何か
大規模修繕工事とは、マンションやアパートなどの集合住宅において、建物の安全性・快適性・美観・資産価値を維持するために実施される大規模なメンテナンス工事を指します。一般的には築10〜15年を目安に実施され、その後も12年〜15年周期で繰り返されることが多く、定期的な計画と予算の確保が必要です。
対象となるのは、屋上や外壁、防水層、廊下・階段といった共用部分の劣化や破損箇所の補修、塗装、張り替えなど。さらには設備面では、給排水管、エレベーター、インターホンなどの交換や更新も含まれることがあります。
重要なのは、居住者の生活に支障をきたさず、長期にわたって建物を健全に保つことを目的とした計画的な工事であるという点です。日々の小修繕とは異なり、規模も予算も大きいため、管理組合やオーナーの判断ミスがそのまま物件価値の低下や住民トラブルに直結するリスクもあります。
また、建物の耐久性や耐震性、防水性などの性能を維持・向上させる観点からも、大規模修繕は重要です。これにより建物の寿命を延ばすだけでなく、長期的に見た維持費の削減にもつながります。
このように、大規模修繕工事は単なる「見た目を整える」工事ではなく、建物全体の健全性を維持するための“投資”であるという意識が必要です。
なぜ大規模修繕工事が必要なのか
集合住宅は時間の経過とともに、風雨や紫外線、地震や温度変化などの自然条件によって劣化が進みます。外壁のひび割れ、鉄部のサビ、屋上防水の剥がれなどが放置されると、雨漏りや構造劣化といった深刻なトラブルにつながる可能性があります。
また、設備面では給排水管の老朽化による漏水や詰まり、エレベーターの故障など、居住者の生活に直結する不具合が起こり得ます。こうした不具合を未然に防ぎ、入居者の安心と快適な住環境を守るために、大規模修繕工事は欠かせません。
大規模修繕工事の対象となる主な箇所
大規模修繕の主な対象となるのは、次のような共用部分です:
- 外壁(ひび割れ、タイル剥離、塗装劣化など)
- 屋上(防水層の老朽化)
- 廊下・階段(床材の劣化、手すりのサビ)
- バルコニー(手すり、床面、排水の確認)
- 給排水設備(配管、排水桝など)
- 共用電気設備(照明、受電盤の更新)
これらの部位は、居住者全員が日常的に利用するものであるため、機能不全が発生すると生活の質に大きな影響を及ぼします。
修繕積立金と大規模修繕の関係
大規模修繕工事は数百万円から数千万円の費用がかかるため、通常は毎月の「修繕積立金」を積み立てて予算を確保します。
修繕積立金の金額が不足していると、居住者からの一時金徴収や借入が必要となり、合意形成が難航したり、住民トラブルに発展することもあります。
そのため、適正な金額を定期的に見直しながら積み立てていくことが、大規模修繕の成功において極めて重要です。
管理組合・オーナーの役割
大規模修繕工事を円滑に進めるうえで、管理組合やオーナーの果たす役割は極めて重要です。
まず、建物の長期修繕計画を策定し、その内容を住民と共有することが基本となります。計画の内容には、工事時期や対象範囲、必要な費用の概算などが含まれます。これにより、将来的な負担を見越して準備することが可能となります。
次に、工事業者の選定や見積もりの比較、説明会の実施など、複数の調整業務を行う必要があります。業者とのやり取りだけでなく、住民との合意形成や説明責任も求められるため、透明性と公平性が欠かせません。
また、実際の工事が始まると、工事の進捗管理や近隣住民への配慮、トラブル対応なども管理組合の責任となります。
こうした負担を軽減するために、第三者管理方式の導入や、修繕専門のコンサルタントを活用する事例も増えています。
大規模修繕は「工事をすること」そのものよりも、「合意を得て計画通りに実行するプロセス」のほうが難しいというのが実情です。だからこそ、経験のある専門会社やコンサルタントと連携しながら進めていくことが、大きな失敗を防ぐ鍵となります。
修繕費の内訳と費用の考え方

修繕費はどのように算出されるのか
大規模修繕工事における修繕費は、「建物の規模」「劣化の度合い」「使用する材料」「施工範囲」「工期」など多くの要素に基づいて算出されます。一般的には、過去の施工事例や劣化診断に基づき、建物全体の現状と将来を見据えた修繕計画に沿って費用が設計されることになります。
たとえば、築15年以上経過しているマンションでは、外壁の塗装だけでなく、屋上防水やバルコニーの床面の修繕、給排水設備の更新なども一括して行う必要がある場合が多く、工事費用は数千万円から数億円規模に及ぶことも珍しくありません。
また、修繕費は「共用部分」に対して使われるため、管理組合の資金計画との整合性も必要です。長期修繕計画に基づいた積立金の推移や、金融機関からの借入可否、補助金の活用可能性なども考慮しながら調整されるため、早期からの資金準備が非常に重要になります。
精度の高い見積もりを得るためには、建物診断の結果をもとに、複数の施工会社から内訳の詳細な見積もりを取り、工事項目ごとに費用構成を確認する必要があります。とくに、劣化診断の精度によって工事範囲も変わるため、第三者機関による中立的な診断も有効です。
材料費・人件費・その他の比率
修繕費の内訳を見ると、大まかに分けて「材料費」「人件費」「仮設・共通工事費」などが主な構成要素となります。
材料費は全体の30~40%を占めることが多く、外壁塗装、防水材、給排水管など、使用する資材の品質や耐久性によって大きく変動します。高耐久塗料や遮熱防水材など、機能性の高い材料を使用すると初期費用は高くなりますが、長期的には修繕周期が伸びることで結果的にコストダウンにつながる可能性があります。
人件費も30~40%程度を占め、工事の規模や工期、職人の技術力によって差が出ます。特に熟練工が必要な特殊施工の場合は高額になりやすく、ここで施工品質の差が生まれることも。
その他、仮設足場や養生、清掃、現場管理費などの共通仮設費が15~20%程度を占め、見落とされがちですが、工事の安全性・円滑な進行に直結する重要な要素です。
業者選定と見積もりのポイント
適正な修繕費を確保するためには、信頼できる業者の選定が欠かせません。施工実績だけでなく、見積もり内容の透明性、過去のトラブル事例の有無、現場監理体制、住民対応力など、総合的に判断する必要があります。
見積もりを比較する際は、単に金額の高い・安いではなく、「何にいくらかかっているのか」という明細を丁寧に精査することが大切です。同じ「外壁塗装工事」でも、足場設置の有無や下地補修の範囲、使用塗料のグレードによって金額は大きく変わります。
また、管理会社が紹介する施工業者にそのまま任せるのではなく、第三者の専門家を交えて相見積もりを取ることで、より客観的な判断が可能になります。
賢くコストを抑える方法とは
費用を安易に削るのではなく、品質を維持しつつ「費用対効果」を最大化するのが賢いコストの抑え方です。以下のような視点が重要です。
- 使用材料の選定:グレードを下げずに耐用年数の長い材料を選べば、次回修繕までの期間を延ばせる。
- 施工範囲の精査:劣化の激しい箇所を重点的に修繕し、問題の少ない部分は軽微な対応にとどめる。
- 工事時期の調整:閑散期(雨期や冬季)を選ぶことで、工事費用が安くなる可能性も。
- 補助金や助成制度の活用:地方自治体によっては修繕に対して補助金が出る場合もあり、これを活用することで大きくコストを削減できます。
いずれも専門知識が必要なため、コスト削減と品質担保を同時に叶えるには、経験豊富な業者やコンサルタントと連携することが有効です。
予算計画の立て方と資金準備
大規模修繕工事は一度の工事で数千万円単位の費用が発生するため、長期にわたる計画的な資金準備が不可欠です。
基本となるのは「長期修繕計画書」です。これは管理組合が建物の築年数、設備の劣化状況、将来的な工事項目を見据えて策定するものであり、その内容に基づいて修繕積立金を毎月計画的に積み立てていく必要があります。
しかし、現実的には修繕積立金だけでまかないきれないケースも多く、以下のような補填手段が検討されます。
- 一時金の徴収:工事直前に各戸から追加費用を徴収するが、住民の負担が重くトラブルの原因にもなりやすい。
- 金融機関からの借入:管理組合名義でローンを組むことで、分割的な資金調達が可能。ただし審査や返済計画の作成が必要。
- 公的補助金の活用:外壁断熱、バリアフリー改修など目的が合えば助成金対象になる場合もある。
資金調達を成功させるためには、計画段階から「いくら必要で、どのように調達し、どう返済・運用していくか」というシミュレーションを立てておくことがカギです。これができていないと、工事直前に資金不足が発覚し、工期の遅れや計画の見直しを余儀なくされるリスクも。
信頼できるパートナーとともに、中長期的な視点で準備を進めておくことで、将来的な建物の価値維持と、住民の安心を確保することができます。
修繕のタイミングと周期

なぜタイミングが重要なのか
修繕工事において「いつ実施するか」というタイミングの選定は、建物の寿命や修繕費用に大きな影響を与えます。適切なタイミングでの修繕は、劣化の進行を抑え、結果として大規模な修繕工事を回避できる可能性を高めます。
たとえば、屋上防水の劣化を放置すると、漏水や鉄筋の腐食につながり、構造体に深刻な影響を及ぼす恐れがあります。そのような事態を防ぐには、早期に劣化を発見し、最小限の範囲で対処することが最も効率的です。加えて、事前に修繕を実施することで、資材や人員の調整もしやすくなり、コスト面でも有利になることが多くあります。このように、修繕のタイミングを見極めることは、コストと品質の両立に直結する重要な判断なのです。
各部位ごとの修繕周期
建物の部位によって、劣化のスピードや修繕の目安となる周期は異なります。
たとえば、外壁塗装は一般的に10〜15年周期での再塗装が推奨されています。屋上やバルコニーの防水層は、使用する防水材によって耐用年数が異なりますが、15〜20年での改修が目安です。給排水管などの設備については、20〜30年での更新が一般的です。これらの周期は建物の立地条件や施工時の品質にも左右されるため、あくまで目安として捉え、実際には定期点検などで劣化状況を把握することが大切です。
長期修繕計画との整合性
マンションなどの集合住宅では、管理組合によって長期修繕計画が策定されています。
この計画は、25〜30年先までの修繕項目や費用をあらかじめ見積もるもので、毎月積み立てられる修繕積立金の使途にも関わる重要な資料です。しかし、実際の劣化状況や経済情勢の変化により、計画と現実が乖離するケースもあります。したがって、定期的な見直しが必要です。見直しの際には、専門家の診断結果を踏まえ、現実的な内容へ更新することで、住民の合意形成も得やすくなります。
定期点検の重要性と診断手法
修繕のタイミングを的確に把握するためには、定期点検が不可欠です。
国土交通省では、3年に一度の簡易点検、6年に一度の精密点検を推奨しています。
点検方法としては、外壁タイルの打診検査、赤外線による漏水チェック、給排水管の内視鏡検査などがあり、これらを通じて劣化の兆候を把握します。
点検結果を基に修繕の優先順位や時期を検討することで、無駄な出費を避けながら効果的なメンテナンスが可能となります。
修繕周期の柔軟な見直しと対応
現代の建物管理においては、画一的な修繕周期に頼るのではなく、実際の使用状況や劣化状態に応じた柔軟な見直しが求められます。
たとえば、近年は環境負荷の高まりから遮熱・断熱塗料の採用が進んでおり、これにより外壁や屋根の劣化が遅くなるケースも増えています。また、在宅勤務の増加により配管設備への負荷が高まっているため、従来よりも早めの対応が必要となる場合もあります。こうした変化を反映するには、専門家との連携や最新技術の導入も重要です。
さらに、修繕周期の見直しは、予算や住民の要望とも調整しなければなりません。住民説明会の開催や、情報提供を充実させることで、合意形成を図ることが成功の鍵となります。
修繕積立金と資産価値の関係性

マンションの資産価値は、立地や築年数だけでなく、修繕積立金の管理と大規模修繕の実施状況によって大きく左右されることが知られています。ここでは、修繕積立金と資産価値の関係について詳しく見ていきましょう。
修繕積立金が適正であることの重要性
修繕積立金は、大規模修繕工事をはじめとする共用部分の維持管理費用を将来にわたって計画的に確保するための資金です。
この金額が適正に設定されていないと、必要な修繕ができず、結果として建物の劣化が進行し、資産価値が大きく下がってしまいます。また、修繕直前になって資金不足が判明すると、急な値上げや一時金の徴収が必要となり、住民の負担が重くなってしまいます。
国土交通省が公表している「修繕積立金のガイドライン」では、目安として1㎡あたり200〜300円程度の積立が望ましいとされていますが、実際には築年数や建物の構造に応じて柔軟な見直しが必要です。
適正な積立金の設定と定期的な見直しが、長期的な建物価値の維持につながるのです。
修繕積立金が少ないマンションのリスク
修繕積立金が明らかに不足しているマンションには、以下のようなリスクが潜んでいます。
- 必要な時期に修繕ができず、劣化が進行する
- 外観や設備の老朽化が目立ち、入居希望者が減る
- 資産価値が下落し、売却や賃貸が不利になる
- 金融機関の評価が低くなり、ローン審査にも影響する
- 突発的に一時金徴収や借入が必要となり、トラブルの原因になる
つまり、住民の経済的負担や資産価値の低下という“負の連鎖”が起きやすくなるのです。
不動産の購入希望者は、「そのマンションの修繕履歴」「長期修繕計画」「積立金の額や使途」などをチェックします。管理状況の透明性がない、または修繕積立金が極端に少ない場合、それだけで選ばれない原因になることもあるのです。
定期的な見直しと長期修繕計画との連携
修繕積立金は、一度設定した金額をそのまま維持し続けるものではありません。むしろ、定期的に見直し、将来の工事に備えて計画的に増額することが現実的です。
たとえば、築年数が浅いうちは修繕の頻度が少ないため積立金を抑え気味にし、築10年・20年・30年のタイミングで段階的に積立額を引き上げる方式(ステップアップ方式)が一般的です。
これにより、住民の負担を急激に増やすことなく、必要な工事費用を着実に確保することができます。長期修繕計画と合わせて積立金の収支を管理することで、計画的かつ無理のない資金確保が可能になります。
重要なのは、長期修繕計画を実行可能な内容にし、それに見合った積立金を確保することです。定期的に建物診断を行い、計画と実情のズレを修正していく姿勢が求められます。
修繕積立金の「見える化」と購入希望者への安心感
最近では、不動産購入希望者や投資家が、修繕積立金の「見える化」を非常に重視するようになっています。
具体的には、
- 管理組合の運営状況
- 修繕積立金の残高と過去の使用履歴
- 長期修繕計画の有無
- 過去の修繕実績
- 積立金の今後の増額予定
などを透明に公開することで、「このマンションは安心できる」という印象を与えることができます。
特に近年は、築年数が経過しても修繕が行き届いているマンションの価値が上昇する傾向が見られます。適切な修繕積立金の運用と情報公開は、物件価値の維持・向上に直結する投資行動といえるのです。
修繕積立金と資産価値を守る管理組合の役割
修繕積立金の適正な管理と積立は、管理会社任せではなく、管理組合自体の責任であることを再認識する必要があります。
理事会の構成メンバーが頻繁に交代する中でも、中長期的なビジョンを持って修繕計画と資金計画を引き継いでいく体制が重要です。
以下のような行動が求められます。
- 長期修繕計画と資金計画の整合性確認
- 修繕積立金の適正額の検討と必要に応じた増額
- 定期的な建物診断の実施
- 専門家(設計事務所・コンサルタント)との連携
- 住民への説明会や情報共有の徹底
これらを通じて、マンションの持続可能性と資産価値を守る“経営”を担っているのが、管理組合であるという意識が何よりも重要です。
専門家との連携と業者選定のポイント

大規模修繕工事を成功に導くには、管理組合だけで完結させるのではなく、専門家との適切な連携と、信頼できる施工業者の選定が極めて重要です。この章では、修繕コンサルタントや設計事務所の活用、そして業者選びの注意点について詳しく解説します。
修繕コンサルタントとは何をするのか
修繕コンサルタントとは、大規模修繕工事の計画・設計・監理までをトータルに支援する専門家です。管理組合と第三者的な立場で関わり、以下のような役割を果たします。
- 現地調査や劣化診断の実施
- 長期修繕計画の見直しと立案
- 工事範囲や仕様の策定
- 見積もり評価や業者選定のサポート
- 工事中の品質管理や工程監理
特に、工事の仕様や金額に透明性を持たせ、適正価格で信頼できる施工業者を選定するサポートは、組合員にとって非常に心強い存在です。
設計監理方式と責任施工方式の違い
大規模修繕工事の発注方式には主に以下の2つがあります。
① 設計監理方式
コンサルタントや設計事務所が仕様を作成し、複数の施工会社から入札を行い、施工と監理を分離して進める方式です。
利点は、透明性が高く、品質管理も第三者が行うため信頼性が高い点。
② 責任施工方式
施工業者が調査・見積・施工を一括で行う方式で、コンサルタントを介さずスムーズに進行できるのが利点。
ただし、第三者のチェックがないため工事品質やコスト面の妥当性に不安が残ることもあります。
コストと信頼性のバランスを考えた上で、どちらの方式が合っているかを判断することが大切です。
見積比較で見るべきポイント
施工業者を選ぶ際、複数社から見積を取得し比較検討するのが一般的ですが、単純に「金額が安いから良い業者」とは限りません。
以下の点に注意して見積をチェックしましょう。
- 工事項目ごとの単価の妥当性
- 使用材料や工法の記載の明確さ
- 足場費や仮設費、管理費などの内訳
- 保証年数やアフターサービスの内容
- 工期や職人の体制、施工管理の有無
不明瞭な点がある業者や、説明責任を果たせない業者は避けるべきです。
逆に、細かく説明し誠実な対応ができる業者は、工事中のトラブルにも柔軟に対応してくれることが期待できます。
トラブル事例と失敗しないための対策
実際に起きた大規模修繕工事のトラブル事例として、以下のようなものがあります。
- 工事中の騒音・振動に対する住民説明不足によるクレーム
- 資材の納期遅延による工期の長期化
- 不具合が見つかったが施工業者の対応が遅い
- 見積金額が途中で大きく増額された
これらの多くは、事前の計画不足や業者選定時のチェック不足によるものです。失敗しないためには、
- 専門家との協働で事前準備を徹底すること
- 住民への説明会を複数回開催し、不安を解消すること
- 契約書や仕様書に工期・金額・品質・保証に関する明確な取り決めを盛り込むこと
が必要です。最も重要なのは、信頼できるパートナー選びと情報共有の透明性です。
業者との良好な関係構築のために
工事期間中は、管理組合と施工業者の連携が成功の鍵になります。業者任せにせず、定例会議や現場視察などを通じて、対話と進捗確認の機会を確保することが重要です。
以下のような姿勢が大切です。
- 指示や要望は文書に残す
- 問題があれば早期に伝える
- 感謝の気持ちを持って対応する
- クレーム処理も冷静かつ建設的に対応する
こうした協力体制の構築が、円滑な工事進行と高品質な施工に繋がるのです。完工後も保証対応やメンテナンスなど、施工業者との関係が続くことを踏まえ、「一時的な発注先」ではなく「長期的なパートナー」としての意識を持つことが肝要です。
よくある疑問と誤解の解消

大規模修繕工事は頻繁に経験するものではないため、住民や管理組合にとって不安や疑問が多いのは当然のことです。この章では、よくある疑問や誤解に対して、専門的な立場からわかりやすく解説します。
大規模修繕工事はなぜ必要なのか?
多くの方が抱く疑問のひとつが、「本当に今、修繕工事をする必要があるのか?」ということです。
これに対して、次のような点が理由になります。
- 建物の劣化は見えないところで進行するため、放置すると安全性や快適性が損なわれる
- 劣化が進んだ状態では修繕費用が高騰しやすくなる
- 将来的な資産価値の維持に直結する
つまり、必要な時期に適切な修繕を行うことは、長期的に見てコストを抑えることにも繋がるのです。
結局、どのタイミングがベストなのか?
大規模修繕工事は「築12年~15年ごと」が一般的な目安とされていますが、立地や使用状況、過去の修繕履歴によってもベストタイミングは変わります。
- 外壁にひび割れや塗装の剥がれがある
- 共用廊下の防水層が劣化している
- 屋上防水が劣化し雨漏りの兆候がある
これらの「劣化のサイン」が現れた場合は、早めの対応が望ましいです。
また、修繕積立金の残高や住民の合意形成状況も、工事時期を左右する要因となります。
修繕積立金で足りない場合はどうすればいい?
修繕積立金が不足している場合、選択肢は以下の通りです。
- 一時金の徴収(住民から追加で費用を徴収)
- 借入(ローン)の活用(金融機関からの借り入れ)
- 工事範囲の見直しや段階的実施(優先順位をつけて分割工事)
ただし、いずれの場合も住民の合意形成が前提となります。
また、計画性がないままの一時金徴収は反発を招くこともあるため、長期修繕計画を見直し、早期の資金対策を講じることが重要です。
工事中の生活への影響は?
「工事中は騒音や臭いがひどいのでは?」といった不安もよくあります。
確かに以下のような一時的な影響は避けられません。
- 高圧洗浄や解体工事による騒音
- 防水や塗装工事による臭気
- 足場設置による圧迫感や採光の低下
- 共用部の一時的な通行制限
ただし、事前の周知や丁寧な対応、工程の工夫により、住民の負担は最小限に抑えることが可能です。
管理組合と施工業者が連携し、こまめな掲示・定例説明会の開催などを行うことで、トラブル回避に繋がります。
業者とのトラブルはどう防げばいい?
施工業者とのトラブルを防ぐには、契約前からの準備と監理体制が不可欠です。
- 契約書には仕様書や工程表を添付し、曖昧な部分を残さない
- 工事中は定例会議や現場監理を定期的に実施
- 問題が発生した場合は速やかに記録を取り、管理組合で対応策を検討
また、第三者である修繕コンサルタントを起用することで、専門的な視点での監理・アドバイスが可能になり、トラブル防止に非常に有効です。
まとめ

大規模修繕工事とは、マンションの資産価値と快適性を維持するために欠かせない大切なメンテナンスです。築10年、15年、そして30年と経年するにつれて、外壁や屋上、防水、設備機器など様々な部分が劣化し始めます。これを放置してしまうと、日常生活の質が損なわれるだけでなく、資産としてのマンションの価値も著しく低下するリスクがあります。
この記事では、大規模修繕工事の意味や内容、周期や費用相場、準備の進め方、トラブル回避策、そして管理組合が果たすべき役割までを丁寧に解説してきました。どれもが、修繕工事を成功させるためには欠かせない知識です。
特に重要なのは、「早めの計画」と「信頼できるパートナー選び」です。修繕費の相場を把握し、無理のない資金計画を立てること。そして、見積もりや工事内容についてしっかりと理解・納得できるまで話し合える業者に依頼することが、後悔しない修繕を実現する鍵となります。
私たち丸投げアパマンは、そうしたオーナー様・管理組合様のご不安やお悩みを「まるっと引き受ける」修繕のプロフェッショナルです。相談・診断・見積もりは無料。修繕の初歩からトラブル予防策まで、ワンストップで支援いたします。
「まずは話だけでも聞いてみようかな」そんなお気軽なお問い合わせも大歓迎です。
company
会社概要

- 屋号
- 丸投げアパマン
- 住所
-
〒350-0252
埼玉県坂戸市中里120-1
- Tel
- 049-277-5445
- Fax
- 049-299-4071
- 営業時間
- 9:00-18:00
- 代表者
- 及川 正義
- 事業内容
- マンション、アパート、工場などの大規模修繕工事専門店
- 運営会社
- 株式会社マルキペイント